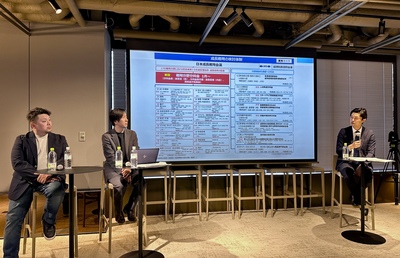競争過熱の全固体電池、EV用は「期待はずれ」に終わるかも
※この記事は公開から1年以上経っています。
実験室では高性能でも…
実は両方とも新しい技術ではない。FCVの実験車第1号が誕生したのは1966年のこと。米ゼネラル・モーターズ(GM)が開発した「Electrovan」がそれ。液体水素を燃料に、航続距離は240km、最高時速は110kmだったという。
全固体電池も1990年代に最初の研究開発ブームが起こっている。当時はペースメーカーのように絶対に液漏れを起こしてはいけない機器向けの小型電池として注目されたのだ。その後、ゲル状の電解質を利用したポリマー電池が普及し、全固体電池の研究開発ブームは一旦終わった...
このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
NEXT STORY
【スポーツクラブ】ルネサンスとゴールドジム、コロナ禍で買収の狙いは?
スポーツクラブ業界で2月に入り、M&Aが立て続けに起きた。買収を仕掛けたのはルネサンスとゴールドジム。新型コロナの逆風下、業界各社はそろって大苦境に陥る中、両社の買収にはどんな狙いがあるのだろうか。
M&A Online
| 2021/2/8
2021.02.08










































.jpg)