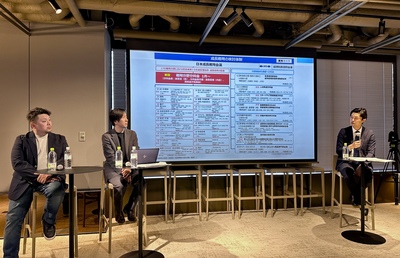岸田首相が全力プッシュしても「合成燃料」では日本車を救えない
※この記事は公開から1年以上経っています。
「これが日本のカーボンニュートラルだ!」岸田文雄首相のお膝元である広島市で開かれる主要7カ国(G7)サミットで、自動車の地球温暖化防止策として事実上、唯一の選択肢だった電気自動車(EV)に加えて、ガソリンエンジン車も合成燃料の利用を条件に生き残る見通しとなった...
このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
NEXT STORY
食品の「値上げ」ペースが加速 2023年は1.53倍に
2023年も食品の値上げが続く。2万822品目(平均値上げ率14%)という記録的な値上げラッシュとなった2022年に引き続き、2023年も1-4月の間に7152品目の値上げが計画されている。
M&A Online
| 2022/12/27
2022.12.27










































.jpg)