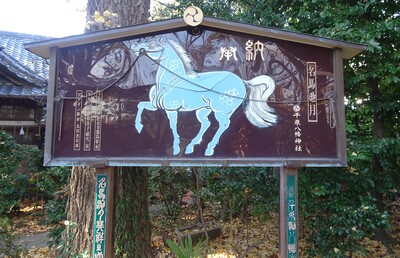IPOを目指すスタートアップの成長を加速するM&A活用術と留意点|EY新日本 IPOグループ統括 藤原選氏に聞く(後編)
※この記事は公開から1年以上経っています。

買収先B/Sに未計上の無形資産等の価値をどう見積もるかが、IPOに影響することも
―「のれん」以外で気をつけた方が良いポイントは何かありますか。
例えば、顧客との契約、商標ブランド、特許権等の法的権利など買収先のB/Sに計上されていない無形資産等に価値があるかどうかも、十分に検討してPPA(Purchase Price Allocation)を行う必要があります...
このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
NEXT STORY
スタートアップ ファーストファイナンスが最重要
2019年に100社の会員企業の中から2、3社のIPOと、10社のM&Aを見込む一般社団法人日本スタートアップ支援協会。代表理事を務めるのは夢展望創業者の岡隆宏さんだ。
M&A Online
| 2019/5/3
2019.05.03