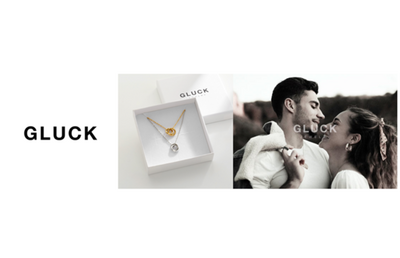IPOを目指すスタートアップの成長を加速するM&A活用術と留意点|EY新日本 IPOグループ統括 藤原選氏に聞く(後編)
※この記事は公開から1年以上経っています。

近年、スタートアップが上場前にM&Aを活用して事業を多角化・拡大してIPOを目指すケースが増えています。第3回はM&Aを成功に導くための法的スキームや会計処理などについて、EY新日本有限責任監査法人でIPOグループ統括を務める藤原選氏(公認会計士)にアドバイスしてもらった...
このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
NEXT STORY
スタートアップ ファーストファイナンスが最重要
2019年に100社の会員企業の中から2、3社のIPOと、10社のM&Aを見込む一般社団法人日本スタートアップ支援協会。代表理事を務めるのは夢展望創業者の岡隆宏さんだ。
M&A Online
| 2019/5/3
2019.05.03