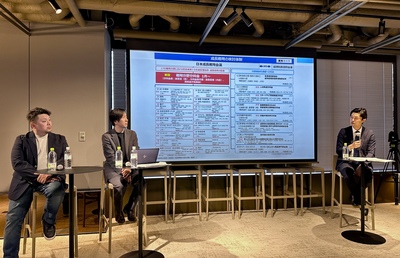【M&A実務】事業譲渡にかかる税金とは
※この記事は公開から1年以上経っています。

事業譲渡によって発生する税金
譲渡会社と譲受会社に対し、それぞれ税金の支払いが生じます。
譲渡会社の税金
事業譲渡により譲渡益が発生した場合、譲渡益に対して「法人税(所得税)」が発生します。ただし、譲渡価額が帳簿価額を下回っていれば、法人税の課税所得が減少します。また、譲渡対象事業に課税資産(在庫や有形固定資産、営業権など)が含まれている場合は「消費税」が発生するほか、「固定資産税」「都市計画税」「償却資産税」があれば、譲渡日前日までの分を負担します...
このコンテンツは会員専用です。
無料会員に登録して、今すぐ続きをチェックしよう!
NEXT STORY
現物出資は意外と使える!活用方法と留意点 しっかり学ぶM&A基礎講座(36)
現物出資は手元資金がなくても資本を増強することができる手法であるのと同時に、グループ会社の組織再編や財務支援の手法ともなり得るものです。
北川ワタル
| 2018/10/8
2018.10.08









































.jpg)