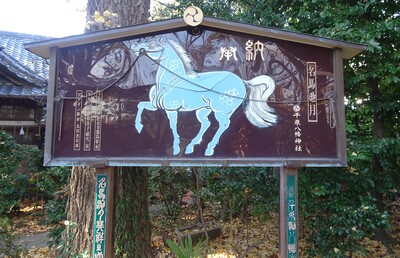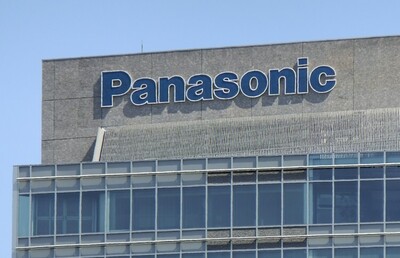【500 Startups Japanトップインタビュー】<2>500 StartupsがJapanをPassしないこれだけの理由
500 Startups Japanトップインタビュー第2回。「Japan Passing」 の風潮があるという中、この時期になぜ日本向けファンドを設立したのか、そして日本での戦略について聞いた。
500 Startups Japan
| 2016/7/7
2016.07.07