
M&Aアーカイブス
上場企業がM&Aを活用して、どのように成長しようとしているのかをまとめています。これまでの歴史や、歴史を踏まえたうえで、今後目指す姿などを取り上げています。
現在の収録数
350社






【YKK】パナソニックHDから住宅設備子会社を買収、LIXIL追撃へ号砲か?
YKKがパナソニックホールディングス傘下で住宅設備を手がけるパナソニックハウジングソリューションズ(大阪府門真市)を買収する。建材・住宅設備でトップに立つLIXIL追撃への号砲となるのか。
M&A Online
| 2025/12/11
2025.12.11
.png)

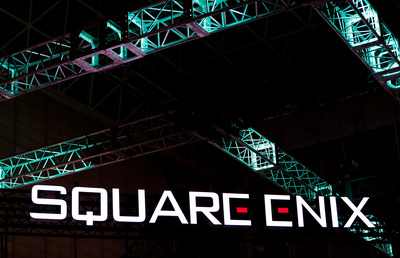

【丸全昭和運輸】創業2世紀を見据えてM&Aを再起動へ、6年ぶりに買収を実行
丸全昭和運輸は総合物流大手の一角を占める。陸・海・空の一貫複合輸送をグローバルに展開する。6年後に控える創業100周年の節目を見据え、M&Aのギアも上げる構えだ。
M&A Online
| 2025/11/13
2025.11.13




.jpg)

【インターメスティック】メガネ業界再編の呼び水か、「Zoff・メガネスーパー」連合が誕生へ
メガネ業界に再編機運がにわかに高まってきた。引き金を引いたのは「Zoff」を展開するインターメスティック。同業大手の一角、「メガネスーパー」の買収に打って出た。
M&A Online
| 2025/9/25
2025.09.25






.jpg)
.JPG)







