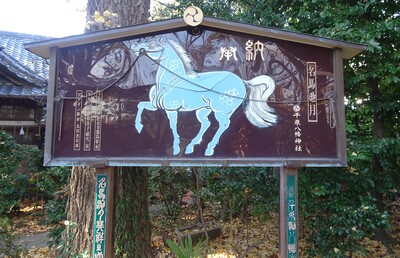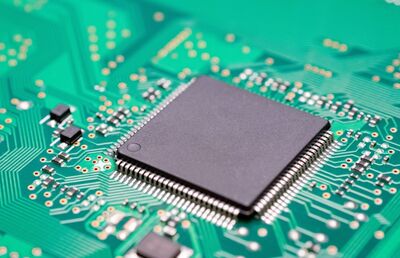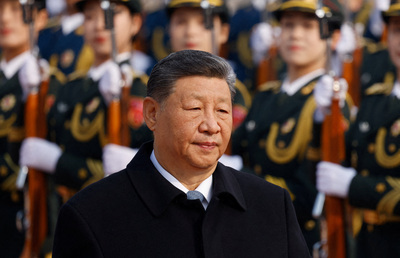【時事】ヤフーのM&Aをめぐる追徴課税は何が問題なのか?
※この記事は公開から1年以上経っています。

画像はイメージです。
ヤフーのM&Aをめぐる追徴課税は何が問題なのか?
ヤフーは、M&Aをめぐる赤字の算入に関連した訴訟で敗訴が続いているようだ。どのような訴訟で、どういった争点があるのだろうか。畑中孝介税理士に聞いた。
訴訟の事実関係の概要をまとめると次のとおり。
2009年ヤフーは、約540億円の繰越欠損金のあるソフトバンクのグループ会社(ソフトバンクIDCソリューションズ、以下IDCS)をソフトバンクから買収、その繰越欠損金を算入したが認められず、追徴課税が行われた...