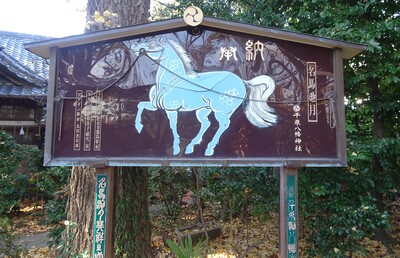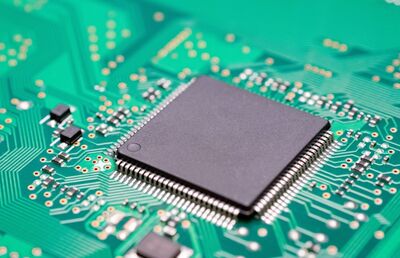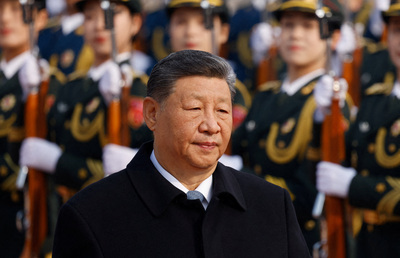【足利銀行】唯一無二だからこそのフェニックス|ご当地銀行の合従連衡史
※この記事は公開から1年以上経っています。

蔵の街・栃木。栃木の金融は栃木市から足利市、県南部で発展してきた(つきのさばく/photoAC)
生まれも育ちも「足利銀行」
地銀の歴史を振り返るとき、多くは「明治期の国立銀行に端を発した」とか「県内有力私立銀行が昭和初期の一県一行主義のなかで大合同して誕生した」といったケースが多い。ところが、足利銀行の場合はそのようなことはなく、1895年に足利銀行として誕生し、現在も足利銀行として存立する。いわば、「生まれも育ちも足利銀行」なのである。
その歴史を振り返っておこう。同行ホームページの沿革を見ると、「1895年10月に栃木県足利町にて営業開始。1914年5月には東京支店を開設...