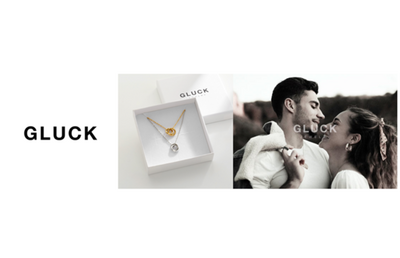4630万円誤振込で判明!フロッピーは、なぜ生き残ったのか?

いまだ現役だったとは!山口県阿武町が新型コロナ給付金4630万円を1世帯に振り込んだ事件で、町役場と金融機関とのデータのやり取りにフロッピーディスク(FD)を利用していたことが判明し、話題になっている。かつてはパソコン用の外部記憶媒体として一般的だったが、現在ではほとんど見かけなくなった。なぜこんな古い記憶媒体が生き残っているのか?
フロッピーが生き残っているのは「誕生した時代」が大きい
FDは磁気記録媒体の一種で、8インチFDが1970年に誕生。1976年に5.25インチ、1980年にソニーが開発した3.5インチと小型化してパソコンに内蔵が可能となり、使いやすさから一気に普及する。しかし、1枚当りの容量が上位規格の2HDで1.6〜2MBと少なかったことから、音声や画像などのデータを取り扱うことができなかった。
そのため2000年以降は光ディスクのCD-ROMや書き込み可能なCD-RAM、ミニディスク(MD)などに世代交代している。その後はCD-ROM/RAMやMD、さらに大容量のDVD-ROM/RAM(最大100GB)ですら保存データの大容量化に追いつかなくなり、外部記憶装置が不要で大容量のフラッシュメモリーやクラウドに置き換わった。そんな時代に、なぜ今さらFDなのか?
そこにはFDの登場した時代背景がある。FDが一般的な外部記憶媒体だった1970〜80年代は家庭用パソコンに先行して中小企業などでオフィスオートメーション(OA)やファクトリーオートメーション(FA)の本格的な導入が始まった時期に当たる。
この時に導入したシステムは、当時最先端だったFDでデータの保管ややり取りをしていた。そのシステムを依然として利用している事業所が意外と残っているのだ。山口県では阿武町役場はもちろん、地方銀行の山口銀行や第二地方銀行の西京銀行もFDでのデータ取り扱いを続けているという。