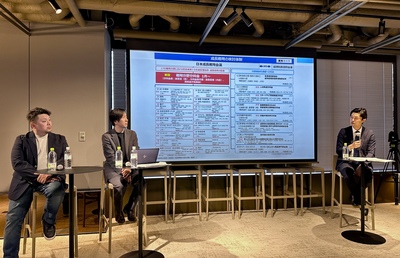JAXA H3ロケット打ち上げ「失敗ではない」強弁のリスクとは
※この記事は公開から1年以上経っています。
新型ロケット「H3」1号機を発射できなかったトラブルは「失敗」だったかどうかが議論になっている。会見で記者団からの「失敗だったのではないか」との質問に、JAXA側は「設計の想定範囲内での事象のため、失敗ではない」で押し通した。ネット上では「失敗」と決めつけた記者の態度に対する反発が広がっているが、今回の中止は本当に「失敗」だったのか?宇宙ビジネスの視点で検証してみよう。
「ビジネス」を強く意識したH3ロケット
「H3」ロケットは宇宙ビジネスに参入するため、国際競争力のあるロケットを目指して開発された...

















.jpg)