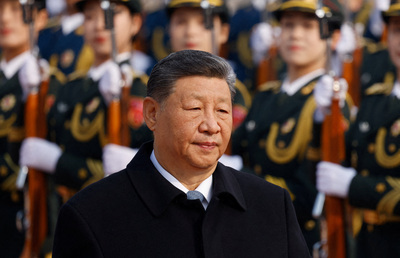[国税徴収法] 「M&Aでも要注意! 第二次納税義務」
※この記事は公開から1年以上経っています。

国税不服審判所の判断
① 財産評価基本通達は相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関する基本的な取扱いを定めたものであり、国税徴収法の第二次納税義務の限度額を算定するための財産の評価に関して、徴収法の規定上、財産評価基本通達を適用又は準用すべきとした規定はないことから、財産評価基本通達に従って算定しなければならないものではない。
② 財産評価基本通達のほか、取引相場のない非上場株式の評価を対象とした基準等としては、日本公認会計士協会が作成した「企業価値評価ガイドライン(平成19年5月16日作成。平成25年7月3日改正)」 (以下「本件ガイドライン」という)がある。
本件ガイドラインは、公認会計士に対して法的拘束力を持つものではないものの、近年のM&Aなど株式評価業務の増加に対応して、日本公認会計士協会が我が国における取引相場のない非上場株式の評価基準及びマニュアルとなり得るものとして、株式の価値を評価する場合の実施及び報告について取りまとめて作成したものであることから、本件差押株式の評価においても、十分参考となる指針であると認められる。
③ 本件ガイドラインによれば、評価アプローチ体系には、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ及びネットアセット・アプローチがあり、具体的評価法には、時価純資産法、類似取引法、配当還元法及びDCF法などがあるとしている。
時価純資産法は、ネットアセット・アプローチの手法であり、貸借対照表の時価評価額を基準に価値を評価する会社の清算を前提とするような場合に相応しい評価方法として、また、DCF法は、インカム・アプローチの代表的手法であり、継続企業としての価値の評価に相応しい評価方法であるとされている。
また、本件ガイドラインにおいては、企業価値などの形成要因は評価対象会社によってさまざまであり、評価法にはそれぞれ長所、短所があることから、価値形成要因が単純である場合は、単独法が採用されるが、そうでない場合は、複数の評価方法の採用、併用又は折衷法のいずれかで総合評価すべきとしている。
これらの評価方法は、実務上、企業の株式評価に広く活用され、さらに判例でも採用されている現状にあり、株式評価の方法として広く認められたものといえる。
④ 原処分庁(国税)は、本件鑑定書における本件差押株式の評価において、財産評価基本通達によらず、DCF法などの評価方法を選択しているところ、上記③のとおり、これらの評価方法は株式評価の方法として広く認められたものであることから、これらの評価方法を選択していることをもって、不合理な点があるとは認められない。
具体的には、継続企業としての価値の評価としてふさわしい評価方法であるDCF法による評価額を算定し、次いで、会社の清算を前提とするような場合に相応しい評価方法である時価純資産法による評価額を算定し、最後に、上記二つの評価方法の平均値をもって、最終的な評価額としているところ、本件鑑定書は、単独法だけではなく、複数法の採用、併用又は折衷法のいずれかで総合評価すべきとした本件ガイドラインに照らして不合理であるとはいえない。
⑤ DCF法は、継続企業としての価値を評価するものであり、将来の事業計画によることが望ましいことはいうまでもないが、本件鑑定人は、本件鑑定書におけるDCF法による算定過程において、本件子会社の将来の事業計画の数値によらず、2012年12月期など過去の決算書などの数値を使用して将来の営業利益などを見積もり、算定している。
しかしながら、これは、原処分庁が本件子会社の事業計画などの資料を入手できなかったためであり、また、継続企業の評価時点において大きな状況の変化がない場合、将来においても現状の損益を維持するものとして算定したとしても、一概に不合理であるとはいえない。特に、本件子会社は、○○という業種の特性があることから、例えば、店舗の新設又は閉鎖、近隣にライバル店舗が出店するなど、評価に大きな影響を与えるような事実が認められない状況下においては、過去の数値により将来の数値などを見積もって算定したとしても、不合理な数値を採用したとまでは認められない。
⑥ 請求人は、本件子会社は、原処分庁から事業計画を提出する機会を与えられず、将来の収益見込みなどについて説明する機会も得られないまま、本件差押株式について時価評価を受けることになったものであり、本件鑑定書は、事業計画に基づいてFCFを予想するという評価の原則に反して作成されたものであり、評価における適正手続に欠けていたものである旨主張する。
しかしながら、原処分庁は、本件滞納法人に対して、本件子会社の株式評価の算定のための資料の提出を求めたが、本件滞納法人からの提出はなかったことが認められる。
そうすると、原処分庁が、本件滞納法人の協力を得られない状況下で、既に把握していた資料を基に本件差押株式の評価を行ったことは、やむを得なかったものと認められ、この点について、適正手続に欠けていたとまでは認めることはできない。
以上、DCF法の一部の計算過程(設備投資額や運転資本減少などの計算要素)に国税不服審判所の修正が加えられたものの、最終的にはおおむね国税側の主張が認められたそうです。














.png)