“大人起業家”が考える「成功するスタートアップ」 プロトスター株式会社・栗島祐介CCO
※この記事は公開から1年以上経っています。

VC経験で感じた日本の起業家支援の貧弱さ
プロトスター自身も創業は2016年というから、業歴そのものは他のスタートアップ系の企業と変わりはないと言うこともできる。では、なぜ、いまこのような立ち位置にいることができるのか。
栗島氏はかつて、上場企業の創業者とともにVC(ベンチャーキャピタル)を作り、アクセラレータプログラムの運営も行っていた。その際に、起業家たちと一緒に住む等、日本中の起業家・投資家とのネットワークを構築していた。そのように、投資やベンチャーの起業・育成・連携といった対応に豊富な実績があったのである...

















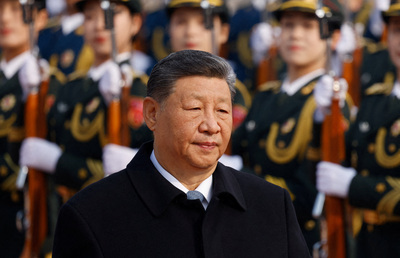
.png)


