【日本煉瓦製造】嗚呼、郷愁の赤煉瓦|産業遺産のM&A
※この記事は公開から1年以上経っています。

煉瓦資料館に展示されている各種の煉瓦
埼玉が生んだ、もう1つの名家
埼玉県には、渋沢家とともに日本を代表するもう1つの名家がある。諸井家。なかでもその11代当主で秩父セメントの創業者である諸井恒平は「セメント王」と呼ばれ、大正・昭和の日本経済の発展に寄与した人物として知られている。
諸井恒平は1862年、深谷に隣接する現在の埼玉県本庄市に生まれた。渋沢栄一の親戚筋にあたり、県北の地場産業である養蚕に従事したのち日本煉瓦製造に入社、専務取締役として経営の舵をとり、東京毛織、武相水電、北陸水電など地元産業や電力という基幹産業の経営に携わる...









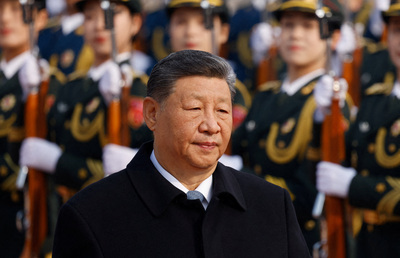
.png)


